療育施設と保育園はどちらも子どもの成長を支える大切な場ですが、目的や支援内容には違いがあります。
本記事では、療育施設と保育園それぞれの特徴や併用方法、費用の目安、施設選びのポイントをわかりやすく解説します。お子さまの発達状況や家庭の方針に合わせて、どちらか一方を選ぶのか、それとも併用するのかを検討しましょう。
自宅近くで安心できる療育施設を探したい方は、全国の療育園や放課後等デイサービスが検索できる「 イクデン」をご活用ください。
>> イクデン公式サイトを見る
療育施設(療育園)と保育園はどんな違いがある?

療育施設(療育園)と保育園は、どちらも子どもが過ごす施設ですが、その目的や支援内容には明確な違いがあります。
保育園は、保護者の就労などで日中の保育を必要とする子どもを対象に、生活習慣の基礎づくりや集団生活への適応を目的として運営されています。一方、療育施設は、発達に特性がある子どもや発達の遅れが気になる子どもに対し、一人ひとりの発達段階に合わせて、成長をサポートする専門機関です。
保育園は集団での生活経験を重視し、療育施設は個別支援計画に基づく支援に力を入れる点が大きな特徴です。どちらも子どもの健やかな成長を目指しますが、アプローチの仕方や支援の重点が異なる点が違いといえます。
療育と保育はアプローチが違えど規定の目標は共通している
療育と保育は支援方法や関わり方に違いはありますが、規定の目標は共通しています。どちらも子どもが心身ともに健やかに育つことを第一に考え、発達をサポートしながら運営する場です。
たとえば、以下のような共通項が挙げられます。
-
子どもの基本的な生活習慣を身につける
-
社会性や協調性を養う
-
その子らしい成長や自立を支援する
-
保護者と連携しながら子どもの育ちを見守る
保育園では日々の生活や遊びを通して、療育施設では個別計画に基づいた活動を通して、いずれも子どもの「できること」を増やします。その結果、将来的な自立や社会参加につなげることを目指しています。
出典:
療育と保育園は併用可能!どうやって連携するのかも紹介
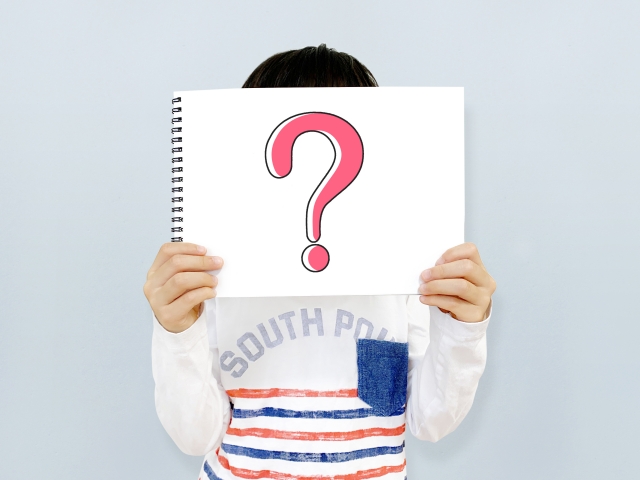
療育施設と保育園は基本的に併用することが可能です。日中は保育園に通い、放課後や休日に療育を受けることで、集団生活と個別支援の両方のメリットを得られます。
ただし、保育園の中には「加配保育士」や「特別支援型」の体制を整え、園内で療育的なサポートを行う施設もあり、併用が不要なケースもあります。併用を検討する際は、まず自治体の担当課や通っている園と相談し、利用条件や連携方法を確認しておくことが大切です。
保育園と療育を並行通園するには受給者証を発行することが必要
保育園に通いながら療育施設も利用する場合は「通所受給者証」の取得が必要です。この受給者証は、お住まいの市区町村の窓口で発行され、支援の内容や頻度を記載した計画書に基づいて利用できます。
計画書の作成方法には2つのパターンがあり、保護者が自分で作成する方法と、相談支援専門員に依頼する方法があります。どちらを選ぶかは家庭や自治体の方針しだいです。
また、3歳から5歳までの無償化対象児童であれば、療育費用がかからない場合も多く、市町村によって負担内容は異なるので事前の確認が必要です。併用を進めたい場合は、まずお住まいの自治体の窓口に相談してみましょう。
保育園から療育を勧められたら発達相談を受けてみるのがおすすめ
保育園での集団生活の中で、言葉や行動、感覚の面で発達の特性が目立つ場合、先生から療育の利用を勧められることがあります。この場合は、まず地域の「発達相談窓口」や「子育て支援センター」に相談してみましょう。
発達相談では、専門スタッフが子どもの発達状況を丁寧に確認し、療育の必要性や利用の流れをアドバイスしてくれます。相談を通じて、子どもの特性に合った支援方法や環境が見えてくるため、不安を一人で抱え込まずに行動へ移していくことが大切です。
なお、窓口は自治体の公式サイトで「発達相談 地域名」と検索すれば見つかります。
保育園と療育施設で並行通園する際のスケジュール例

保育園に通いながら療育施設を併用する場合、利用する時間帯によって通い方のパターンが変わります。ここでは以下の代表的なスケジュール例を紹介します。
-
平日・保育園の利用時間内に使う場合
-
平日・保育園の利用時間以外で使う場合
-
休日・保育園が休みの日に利用する場合
平日・保育園の利用時間内に使う場合
平日・保育園の利用時間内に利用する場合は、保育園の一部時間を抜けて療育に通います。たとえば午前中に保育園で過ごしたあと、午後に療育を受ける流れが一般的です。
<スケジュール例>
-
8:30〜12:00 保育園で通常保育
-
12:00〜13:00 昼食・移動
-
13:00〜15:00 療育施設で活動
-
15:30〜16:30 保育園に戻って延長保育(希望があれば)
園内での集団生活と個別支援を1日の中で組み合わせられるのが特徴です。送迎や時間調整の負担はありますが、子どもがその日のうちに両方のサポートを受けられるメリットがあります。
平日・保育園の利用時間内に使う場合は、園と施設の連携が必要です。送迎時間などの調整も欠かせないので、各方面とよく連携をとりましょう。
平日・保育園の利用時間以外で使う場合
平日・保育園の利用時間以外で使う場合は、保育園が終わったあと夕方以降に療育施設へ通います。日中は保育園で過ごし、帰りに療育を受けるイメージです。
<スケジュール例>
-
8:30〜15:30 保育園で通常保育
-
16:00〜17:00 療育施設で活動
-
17:30〜18:00 帰宅
日中のリズムを崩さず、習いごとのように療育を追加できるのが特徴です。園での活動量が多くなるため、子どもの体力や集中力を考慮したうえで選びます。
夕方からの時間帯を選ぶ場合は送迎の負担が大きくなるため、無理のない距離の施設を選ぶことがポイントです。
休日・保育園が休みの日に利用する場合
休日・保育園が休みの日に利用する場合は、平日は保育園だけに通い、休日に療育施設を利用します。
<スケジュール例>
-
9:30〜11:30 療育施設で活動
-
12:00〜13:00 昼食
-
13:00以降 家庭で休息・遊び
休日を利用することで、平日は生活リズムを崩さず園生活に専念できるため、休日に落ち着いた環境で個別支援を受けられます。保護者も参加しやすい日程に設定しやすく、家庭での関わり方を学べるのがポイントです。
無理のないペースで療育を受けたい場合や、送迎時間を確保しやすい家庭で多く採用されています。
子どもにぴったりな療育施設・保育園を選ぶために注目したい6つのポイント

療育施設や保育園を選ぶ際には、立地や雰囲気だけでなく、専門性や支援体制も大切です。以下のポイントを意識して選ぶことで、子どもに合った環境を見つけやすくなります。
-
園の療育実績や支援経験が豊富であるか
-
加配保育士や専門職(ST・OTなど)が在籍しているか
-
通いやすいか(自宅からのアクセスの良さ)・送迎サービスがあるか
-
療育方針や支援スタイルが家庭のものと合っているか
-
GoogleMap等での良い口コミが多数掲載されているか
-
保育園が母体で児童発達支援や放課後等デイサービスも提供しているか
①園の療育実績や支援経験が豊富であるか
園を選ぶときは、どれだけ療育に関する経験や実績があるかをまず確認しましょう。療育のノウハウを持った園では、発達特性への理解が深く、子ども一人ひとりに合った対応が期待できます。
とくに、これまでにサポートしてきた人数や支援年数の情報は実績として参考になります。経験豊富なスタッフが揃っている園は安心して任せられるため、見学時に実績について質問してみるのもおすすめです。
②加配保育士や専門職(ST・OTなど)が在籍しているか
療育が必要な場合、言語聴覚士(ST)や作業療法士(OT)などの専門職、また加配保育士が在籍しているかが重要です。加配保育士とは、特定の子どもに対して手厚い支援が必要な場合に、通常の保育士配置数とは別に追加で配置される保育士のことです。
専門職が在籍する園では、発達をサポートする個別プログラムの提案や課題解決の方法をアドバイスしてくれます。預けている間の子どもの安全性の確保はもちろん、個別指導や自由時間の過ごし方をもとに家庭で生かせる的確なフィードバックを受けることが可能です。
通常の保育よりも園と密に連携するからこそ、専門スタッフの存在は子どもを預けるうえで安心材料にもなりますので、事前に体制を確認しましょう。
③通いやすいか(自宅からのアクセスの良さ)・送迎サービスがあるか
通園時間や距離が長いと親子ともに負担になりやすいため、自宅からの距離やアクセスの良さは重要といえます。近くの園を選ぶことで送迎にかかる時間や体力的な負担を軽減できます。
また、送迎サービスを行っている施設もあるため、移動が難しい場合は送迎対応の有無を確認すると安心です。無理なく通える園を選ぶことは継続のしやすさにつながります。とくに、小さな子どもや兄弟がいる家庭では、アクセスの良さが通園を続けるうえでカギとなるでしょう。
④療育方針や支援スタイルが家庭のものと合っているか
園によって療育の方針や支援スタイルは異なります。家庭で大切にしたい子育ての方針や価値観と合っているかを見極めることが大切です。
見学の際にどのような声かけをしているか、活動の雰囲気が子どもに合いそうかを事前にしっかり観察しましょう。家庭の意図を汲んで柔軟に対応してくれる園であれば、園と家庭の協力体制が取りやすくなります。
方針が合う園を選ぶことで、子どもも安心して通え、子どもの成長に一貫性を持たせやすくなります。
⑤GoogleMap等での良い口コミが多数掲載されているか
園選びの参考として、GoogleMapや口コミサイトに掲載されている利用者の声を確認する方法もあります。実際に通っている保護者の感想から、職員の雰囲気や対応、施設の清潔さなどが見えてきます。
良い口コミが多い園は、利用者満足度が高く、信頼されている施設であることが多いです。口コミを複数確認することで、園の雰囲気や支援姿勢の傾向が把握でき、選ぶ際の参考になるでしょう。
⑥保育園が母体で児童発達支援や放課後等デイサービスも提供しているか
保育園が母体となり、児童発達支援や放課後等デイサービスを併設している施設もあります。こうした園では、成長に応じて必要なサービスを同じ場所で受けられるため、別々の施設に通う負担が少なく済みます。
一ヶ所で一貫したサポートが受けられると、子どもも保護者も安心して通い続けやすいため、該当する施設は候補の一つとしてぜひ検討しましょう。
自宅や学校の近くでお子さまに合った療育園を探すならイクデンをご利用ください

自宅や学校の近くでお子さまに合った療育園をお探しなら、ぜひイクデンをご利用ください。
イクデンは、全国の放課後デイサービスや児童発達支援など8万件以上の療育施設情報を簡単に検索できるプラットフォームです。お住まいの地域や通いやすさ、送迎の有無、専門職の在籍状況など、条件を細かく絞って検索できるため、あなたのご家庭にぴったりな療育施設を見つけられます。
各施設の口コミや評価、在籍する専門職(ST・OTなど)、療育プログラムの内容まで確認できるので、比較・検討もかんたんです。また、施設の空き状況の確認や問い合わせがWeb上で済むので、療育園探しを負担に感じることもほとんどないでしょう。
もちろん保育園と療育施設の両方の役割を担う施設も、多数掲載中です。まずはイクデンに無料で登録いただき、お子さまが楽しんで通える園はあるか、ぜひご確認ください。
>> イクデン公式サイトを見る
療育施設(療育園)・保育園を利用する際の費用相場

療育施設と保育園では料金の仕組みが異なります。東京都23区を例にすると、保育園は家庭の所得や年齢によって月額が決まり、0〜2歳であればおよそ月1万〜5万円です。
3歳以上になると国の幼児教育・保育無償化制度により保育料はかからず、給食費などの実費のみの負担になります。認可外や企業主導型保育園の場合は月5万〜7万円になることもあります。
一方、療育施設(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)は、市区町村から「通所受給者証」を発行してもらえば原則1割負担で利用可能です。世帯収入に応じて月の上限額が決まります。
多くの世帯では月額4,600円が上限、3〜5歳児は無償化の対象となるため利用料はかかりません。送迎費やおやつ代などの実費のみ発生します。以下の表は保育園と療育施設の費用を比較したものです。
項目 | 保育園(認可園) | 療育施設(児童発達支援・放デイ) |
0〜2歳 | 月1〜5万円程度 | 上限4,600円 (原則1割負担) |
3〜5歳 | 無償化 | 無償化(0円) |
送迎費用 | なし | ガソリン代など (送迎が必要な場合) |
その他 | 月5〜7万円程度 (認可外の場合) | おやつ・教材費など |
0〜2歳の間は保育園の費用負担が大きい傾向があり、3歳以上になるとどちらも無償化制度が適用され、費用差はほとんどありません。
出典: 保育料表(認可保育園)|練馬区
「療育園」と呼ばれる施設の特徴を種類ごとに解説

療育支援を受けられる施設にはさまざまな種類があります。ここでは以下の代表的な5つの施設形態を挙げ、それぞれの特徴を簡単にまとめましたので選ぶ際の参考にしてください。
-
放課後等デイサービス
-
児童発達支援・児童発達支援センター
-
保育所等訪問支援
-
居宅訪問型児童発達支援
-
障害児入所施設(福祉型・医療型)
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、6〜18歳までの就学児童を対象に、放課後や長期休暇中に療育を行う施設です。学校の授業が終わったあとや夏休みなどの期間に通い、日常生活訓練や学習支援、社会性の向上を目的とした活動が行われます。
子ども一人ひとりの特性に合わせた個別支援計画に基づいて支援が行われ、送迎をしてくれる事業所も多くあります。保護者の就労支援の役割もあり、家庭と学校をつなぐ大切なサポート機関です。
児童発達支援・児童発達支援センター
児童発達支援は、未就学児(0〜6歳未満)を対象に、発達を促す遊びや活動を通じて、日常生活の基礎を育む施設です。児童発達支援センターはその中心的な役割で、集団での活動のほかに専門職による個別指導も行います。
保護者との相談支援も含めて、生活習慣、言語、運動、社会性の面をバランスよく伸ばしていくプログラムが整備されているのが特徴です。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援は、療育の専門スタッフが保育園や幼稚園、認定こども園、小学校などに直接訪問し、在籍している子どもをサポートするサービスです。園や学校での集団生活の中で困りごとがある場合に、適切な支援方法を現場で提供するのが目的です。
たとえば、友達との関わりが苦手な子どもへのサポート方法を現場で示し、集団行動への参加をスムーズにする工夫を行います。また、現場の先生にも支援方法のアドバイスを行うため、子どもにとって安心して生活できる環境づくりをチームで進められることが大きな特徴です。
家庭や療育施設に通うだけでなく、普段の生活の場で直接支援を受けられる点が大きなメリットであり、通所が難しい子どもにとって有効なサポートです。
保育所等訪問支援を通じて、園や学校全体でのサポート体制が強化されるという効果もあります。さらに、保護者と教育現場の橋渡し役としての役割も担っており、子どもの成長を一緒に支える関係づくりを目指します。
出典: 保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書|厚生労働省
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援は、医療的ケアや重度の障がいにより通所が難しい未就学児を対象に、専門スタッフが自宅を訪問して療育を行うサービスです。家庭の中で発達を促す遊びや生活動作の練習を行い、保護者にも支援方法を伝えながら成長をサポートします。
外出が難しい家庭でも継続的に専門的な支援を受けられるのが特徴です。
出典: 居宅訪問型児童発達支援に係る報酬・基準について|厚生労働省
障害児入所施設(福祉型・医療型)
障害児入所施設は、家庭での生活が難しい子どもを対象に、生活の場としての支援と療育を提供する施設です。福祉型は生活訓練や社会性の育成を中心に行い、医療型は医療的ケアが必要な子どもに医療と療育を組み合わせてサポートします。
長期間の入所により、日常生活の習慣づけや将来の自立を目指す総合的な支援が受けられるのが大きな特徴です。
お子さまの状況に合わせて療育園・保育園は使い分けや併用を検討しましょう

療育施設と保育園は目的やサポート内容が異なるため、お子さまの発達状況や家庭の希望に応じて最適な環境を選ぶことが大切です。
両方の特性を生かした併用も可能で、通園スケジュールや費用の仕組みを理解すれば、無理のない形で支援を受けられます。また、園の方針や専門スタッフの有無、アクセスのしやすさも選ぶ際の大事なポイントです。
自宅や学校の近くで安心して通える施設を探すなら、全国の療育施設・放課後等デイサービス情報を網羅した検索サイト「 イクデン」をご利用ください。地域や条件で絞り込める機能や口コミの情報量も充実しているので、お子さまに合った施設を効率よく見つけられます。
通い続けやすく療育・保育の両方を任せられる園をお探しの方は、イクデンをぜひご活用ください。お子さまの成長に合った最適な環境を見つける一歩として、まずは情報収集から始めてみましょう。
>> イクデン公式サイトを見る
なお、イクデンでは療育・保育施設の関係者様向けに無料掲載の希望も承っております。「施設情報を無料で掲載したい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ イクデンへ気軽にお問い合わせください。
>> 療育・保育施設の関係者様向け「イクデン」の無料掲載について問い合わせる
.png/256)




